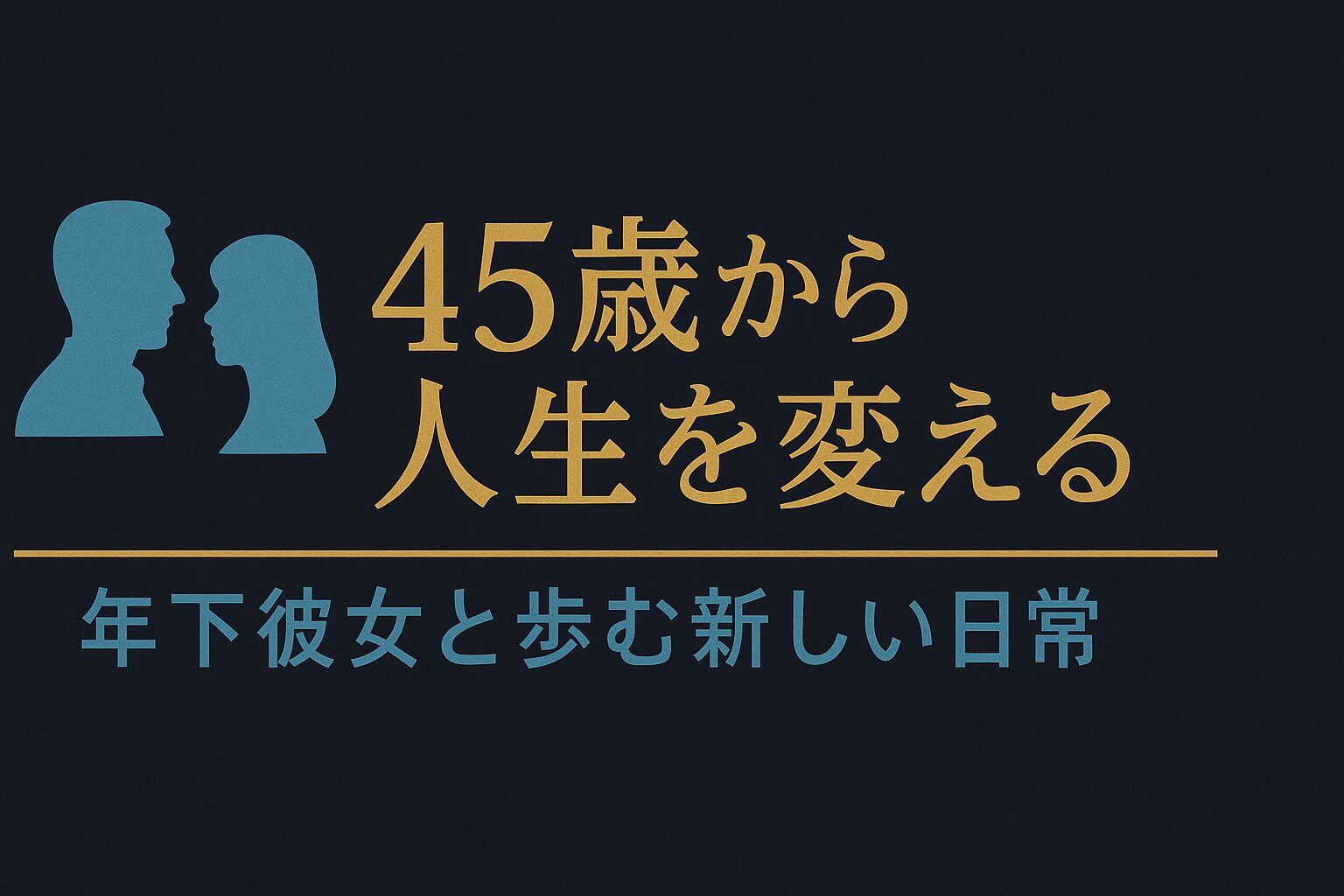はじめに
2025年10月17日(金)に公開された、時代劇映画『おーい、応為』(以下「本作」)は、江戸時代を舞台に、名だたる浮世絵師・葛飾北斎の娘であり弟子でもあった、女性絵師・葛飾応為(通称:お栄)の人生に迫る物語です。
原作に、飯島虚心『葛飾北斎伝』(岩波文庫)および杉浦日向子『百日紅』(筑摩書房)を採用し、監督・脚本を務めるのは『MOTHER マザー』や『星の子』などで人間の内面に寄り添ってきた、大森立嗣。主演には、長澤まさみ。時代に先駆け、男性中心だった浮世絵の世界で己の道を切り拓いた応為の姿が、時に激しく、時に静かに描かれます。
「女性の絵師」「父と娘」「師と弟子」という多層的な関係性を背景に、“絵を描くことに捧げた人生”という普遍的なテーマが、現代にも響く形で切り取られています。筆を握るときの手の震え、長屋の暮らし、父の影、世間の視線……そんな細やかな営みと心の動きを、ぜひスクリーンで味わって頂きたい作品です。
🎬 映画情報
- 監督・脚本:大森立嗣
- 原 作:飯島虚心『葛飾北斎伝』/杉浦日向子『百日紅』(「木瓜」「野分」)
- 主 演:
- お栄/葛飾応為:長澤まさみ
- 善次郎/渓斎英泉:髙橋海人
- 初五郎/魚谷北渓:大谷亮平
- 元吉:篠井英介
- 津軽の侍:奥野瑛太
- こと:寺島しのぶ
- 鉄蔵/葛飾北斎:永瀬正敏
- その他:和田光沙、吉岡睦雄、早坂柊人、笠久美、一華、小林千里
あらすじ
youtube 東京テアトル公式チャンネルより引用
江戸時代、名声を博した浮世絵師・葛飾北斎(鉄蔵)は、多くの弟子を抱えつつも、家では娘お栄と師弟・父娘として暮らしていました。お栄は、ある絵師に嫁ぎますが、その夫の“かっこうばかり”の絵を見下すかたちで離縁して、父のもとへ戻ります。
長屋で父と暮らし始めたお栄の生活は決して豊かではなく、画材や絵で散らかる長屋で、茶も入れられず針仕事もままならない日々。そんな環境の中で、お栄は父譲りの絵の才を少しずつ花開かせていきます。あるとき、父が「おーい、筆!」「おーい、飯!」と口癖のようにお栄を呼ぶことから、“応為(おうい)”という号が与えられ、男性中心の世界で女性として絵師の道を歩み始める。
\映画「おーい、応為」の公式ホームページも是非参照ください/
映画『おーい、応為』公式サイト | 10月17日(金)公開
感想
父の大きな壁を越えようとする娘の苦悩と成長
本作で印象深かったのは、応為がおそらく感じていたであろう「父=大絵師・北斎」という巨大な存在へのプレッシャーです。父の絵師としての名声、弟子たちの期待、そしてその陰で娘として師として生きるという二重の役割。応為が自身の絵を確立していく過程は、現代に生きる私たちにも通じるものがあります—親世代の背中、社会の価値観、自分の道、それらをどう受け止めるか。
長澤まさみが演じるお栄/応為は、ただ壁を見て怯えるのではなく、“自分の手で筆を握る”という明確な覚悟を見せています。そして、父の認められる瞬間――「応為」という名を与えられる瞬間――その喜びを素直には言えず、かみ殺してしまうような、しかし確かに内に味わう歓びの機微を、長澤は丁寧に演じています。
感情の爆発ではなく、息を潜めた震え。膝を抱えた夜、筆を置いて見つめる画面、父の背中を見上げる視線。そういった演出が、応為という女性の強さと脆さを同時に浮かび上がらせていました。
尊敬と伝えられない想い――父娘・師弟の葛藤
また、応為という存在は“尊敬する父”に対して、そのままの言葉では向き合えない。父の傍らで、師弟として、娘として、自分の絵を描いていく。父から “弟子” の名を与えられ、しかしその背後に「娘」であるというプライベートな時間もある。この境界線が曖昧であるからこそ、応為の抱えた葛藤はリアルに映ります。
例えば、父と交わす言葉がぎくしゃくする場面。父が師匠として指を差し、応為が自分の筆を動かす姿。父娘としての距離と、師弟としての距離。応為の心情を観ながら、「ああ、こんな距離感、私にも覚えがあるな」と思わず共感してしまいました。
彼女は父を尊敬し、しかしその想いを「ありがとう」ではなく、「わかってるよ」という態度でしか示せなかった。そこにあるのは、女性として、絵師として、自分を立てたいという矜持。長澤まさみはその複雑な感情の絡まりを、“押し殺す歓び”というかたちで演じ切っており、観る者としても静かに胸を打たれました。
絵の道に憧れ、終わりなき道を見つめる――生涯を描く者の静かな覚悟
さらに、本作には“仙人に憧れる”という描写が随所にあります。北斎も応為も、絵を描くことを自身の人生に据え、時代を駆けながら、絵の奥深さに気づき、憧れ続ける。つまり、「絵の道を究めるには、人の身では時間が足りない」という暗黙の想いが映像の裏にあります。
北斎が90歳まで生きたという史実からも、その執着に近いものがうかがえますが、一方で「歳を重ねていくほどに、感動する心が少なくなっていく」というジレンマもまた、本作の中で描かれていました。
金を積まれても描かない、という北斎の言葉が象徴的です。技術が備わったとしても、心が動かされなければ描けない。まさに、絵師という職業が“生涯を以てしてもようやく入り口に立つような”ものであることを、映像を通じて強く感じました。
そして最終盤、北斎が“富士(=不死、または父子・永続の象徴)”を描き上げた後、倒れるようにその生を終える。応為がその姿を看取り、「もういいんだよ」と囁く瞬間には、「終わりなき絵の道を終わらせること」の肯定が込められているようで、救いに近いものを感じました。
応為のその一言が、「父として/師として/絵師として」の北斎を救ったのかどうか――直接の答えは示されませんが、観る者としては「救われたのではないか」と思いたくなるほど、温かな余韻が残りました。
登場人物・演技・世界観について
出演者・演技面においても見どころが多かったです。長澤まさみは、本作が自身初の時代劇映画主演でありながら、違和感を感じさせず、江戸の長屋、煙草と犬と絵筆に囲まれた“ある女”として自然に存在していました。
永瀬正敏演じる北斎も、ただ偉大な父ではなく、時に人間らしい弱さ(感動できなくなってしまうなど)を抱えた“画家としての老年”として丁寧に描かれており、その存在感が応為との関係性を深く見せていました。髙橋海人演じる渓斎英泉(善次郎)も、時代劇初挑戦とは思えぬ色気と佇まいで、“応為と北斎”という枠に収まらないもう一つの絵師の道を示してくれました
また、江戸の庶民の暮らし、長屋の散らかった画材、火事や飢饉の影響、筆跡のひとつひとつ……映像美としても心地よく、それらがただ“絵を描く”というテーマを補強していました。
総評 & オススメな人
総評
本作は、絵を描くという行為を通じて、父と娘、師と弟子、女性として、芸術家として生きることの意味を描き出しています。そしてその描き方は過度にドラマティックではなく、むしろ静かで、しかし芯が通っていて、その静けさが深い余韻を残します。
「父という大きな壁を越えようとする娘」「尊敬と素直に伝えられない想い」「終わりなき絵の道に寄り添う覚悟」――こうしたテーマひとつひとつが、現代を生きる私たちにとっても刺さります。特に「親の背中を見て育つ」「女性として自分の道を切り拓く」「芸術に生きる」というキーワードに共感を覚える方には、ぜひスクリーンで観て頂きたい作品です。
個人的には、応為が「もういいんだよ」と父に言った瞬間に、観ていた自分自身も「もういいんだよ」と優しく言われたような気がしました。その瞬間、その言葉、その空気が、この物語をただの伝記ドラマではなく、“心の旅”にしてくれたのだと思います。
『おーい、応為』は、ただ過去を振り返る映画ではなく、時代を越えて響く“生きること=描くこと”を描いた作品です。演出・脚本・演技・映像すべてにおいて丁寧に作り込まれており、派手なアクションや過剰なドラマ展開を求める方には静かすぎるかもしれませんが、むしろその“静けさ”が本作の魅力です。
女性絵師という希少な存在を主人公に据え、父と娘の関係性、師弟関係、その中で独り立ちしていく姿を“絵を描く”という行為を通じて描く。この構図が、シンプルながらも奥深い感動を呼び起こします。
こんな人にオススメ!
- 親子・師弟といった“人間関係の深み”を丁寧に描いた映画が好きな方
- 日本美術、浮世絵、江戸時代といった背景に興味がある方
- 女性が芸術の世界で生き抜く姿に共感を覚える方
- 長澤まさみの演技、あるいは大森立嗣監督の作品が好きな方
- 静かな語り口の映画を、余韻とともに味わいたい方
逆に、少し注意されたい方
- アクション・ハイスピード展開・派手な演出を求める方には、ややテンポがゆったりと感じられるかもしれません。
- 知識がゼロの状態で「絵師/浮世絵」の背景から詳しく学びたいという方には、説明が最低限にとどまるため、予習をしておくとより楽しめるでしょう。
※映画紹介についての一連の記事はこちらにまとめていますので、是非一読ください。