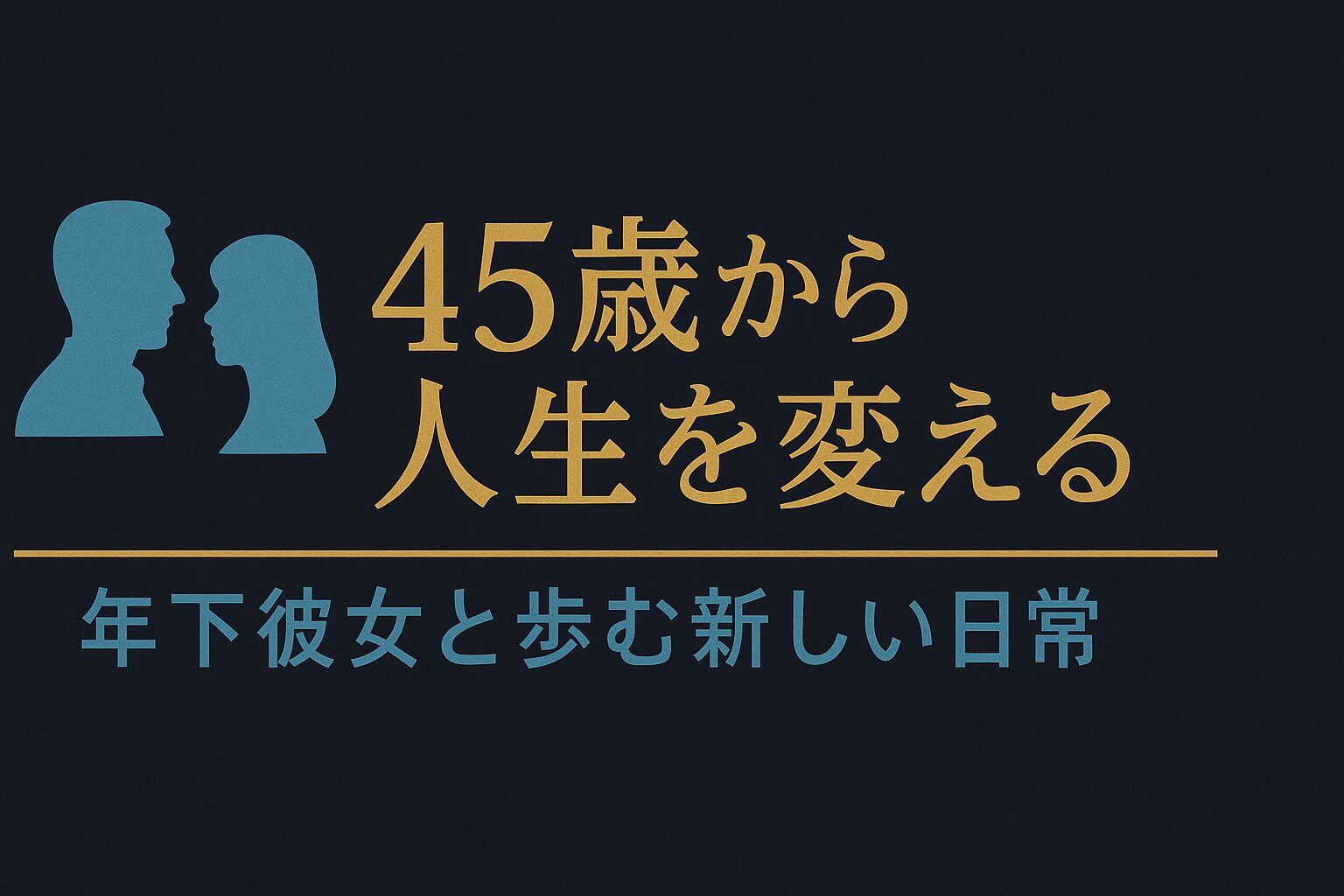はじめに
2025年9月5日に劇場公開された『遠い山なみの光』は、ノーベル文学賞作家:カズオ・イシグロのデビュー小説(1982年)を、石川慶監督が映像化したヒューマン・ミステリーです。広瀬すずや二階堂ふみ、吉田羊、松下洸平、三浦友和ら複数世代の女性たちを中心に描かれる「記憶」「嘘」「赦し」の物語は、静かな感動と深い思索に満ちています。
🎬 映画情報・概要
- 監督・脚本:石川慶(『ある男』で日本アカデミー最優秀作品賞など8部門受賞)
- 原作:カズオ・イシグロ(ノーベル文学賞作家。デビュー作)
- 共同製作:日本・イギリス・ポーランド
- キャスト:
- 悦子(1950年代・長崎):広瀬すず
- 佐知子:二階堂ふみ
- 悦子(1980年代・イギリス):吉田羊
- 緒方誠二:三浦友和、緒方二郎:松下洸平 他
あらすじ:戦後長崎と闇の記憶を巡る母と娘の旅
youtube ギャガ公式チャンネル より引用
1980年代のロンドン。大学を中退し作家を目指すニキ(カミラ・アイコ)は、亡き姉との交流を避けていた母・悦子を取材しに、久しぶりに日本の実家を訪れます。長崎で原爆を経験し戦後英国へ渡った母を、ニキはほとんど知らず、口も閉ざされたままでした。
数日をともに過ごすうちに、悦子は1950年代の長崎で出会った佐知子とその娘の夢の話を語り始め、その淡い記憶が徐々に真実と幻覚の狭間へと侵入していきます。やがて、ニキは母の記憶に含まれる“嘘”を感じ取り、本当の過去へと辿り着こうともがきます。
\遠い山なみの光の公式HPも是非参照ください/
映画『遠い山なみの光』
考察|母の記憶を再構築する意味とは
① “佐知子”とは誰だったのか?──「もう一人の悦子」という影
物語の中で悦子が語る、1950年代・長崎で出会った女性・佐知子とその娘のエピソードは、初見では彼女の「他者としての記憶」として語られます。しかし、観客が次第に悟るのは、佐知子=悦子自身であり、その物語は「自分自身にとって語りたくない過去」を、“第三者の物語”として分離した形式で記憶しているという構造です。
この記憶のトリックは、**「自分の過去を第三者視点で語ることで、自我を保つ」**という心理的防御反応として成立しています。悦子は過去を「事実」として受け止められず、「佐知子の話」として間接的に語ることで、ようやく思い出すことができたのです。
この構造は、皆どこかで「自分の人生をありのまま受け止めきれず」、美化し、再編集し、嘘と真実が混ざった“物語”を通して、ようやく自分の存在と折り合いをつけています。
② 「嘘」とは何か──罪と向き合う手段としての物語
悦子が語る記憶の中の“嘘”は、単なる欺瞞や隠蔽ではありません。それは彼女が生き抜くために必要だった、“自分の罪を受け止める準備期間”でもあったと言えるでしょう。
彼女が英国に渡り、自由な生活を選んだ一方で、その代償として「景子(亡き長女)」の心は次第に蝕まれていった。その責任を無意識に感じていた悦子は、その痛みから逃れるために、自らの人生を“誰か別人の物語”として語る必要があったのです。
この視点から見れば、悦子の語る「佐知子の話」は、赦しを得るための試みです。誰かに責めてほしいわけでも、同情してほしいわけでもなく、ただ「話すこと」が重要なのです。
それが、後年ニキという娘に“語る”という行為を通じて実現し、悦子はようやく自分の過去と向き合う準備が整ったのだと考えられます。
③ 「景子の死」は何を象徴しているのか?──罪、継承、そして喪失
悦子の長女・景子は、生前に精神を病み、自ら命を絶っています。この事実は劇中で多くを語られませんが、観客に強烈な印象を与えます。
このことは、母である悦子の「過去を切り捨てた選択」の象徴的な結果とも言えます。日本からイギリスへ渡った悦子は、戦後の抑圧からの解放を求めて新天地で生きようとしますが、その過程で文化の断絶、言葉の壁、孤独感、そして家族間の心の距離を生んでしまった。
景子は、そうした「母の選択の影」によって苦しみ続けた存在なのです。「景子」は、悦子にとって赦されない罪であり、自分の選択の代償でもあります。
そして、その罪から悦子が逃げ続けた時間が、「佐知子という人物」の創造であり、「記憶の改ざん」だったのです。
④ ニキの視点の意味──次世代が“物語”を修復する
ニキは映画の中で最も現代的な存在であり、母の語る過去に違和感を抱き、自分の手で調べ、確かめ、受け止めようとします。
つまり、ニキは記憶の継承者であると同時に、その“補完者”でもある。母が語りきれなかったこと、嘘をついたこと、罪を抱えてきたこと。それらを正面から受け止め、赦し、未来へ繋ごうとする存在なのです。
カズオ・イシグロの作品には、「語られなかったことの重さ」が常にあります。『遠い山なみの光』は、語られなかったことを次世代が拾い集め、再構成し、未来へつなぐ儀式のような物語です。
⑤ 山なみの“光”とは何か──儚くも確かな希望の象徴
映画タイトルにもなっている「遠い山なみの光」とは、一見すると詩的な風景描写のように思えますが、これは記憶の彼方にある希望の象徴です。
それは「過去に戻れないけれど、確かにそこに存在した何か」であり、人間が記憶を通して未来に希望を見い出す過程を象徴しています。遠く、手の届かない場所にあるけれど、見えている。それだけで、人は前を向ける。
悦子が最終的に語るその風景は、失われた過去への郷愁であると同時に、今を肯定するための光となっています。
評価まとめ:感情を抉り出す静かな世界の力
- 肯定評価:「記憶、後悔、赦しを透徹した瞑想として描く傑作」
- 映像美賛辞:小津や成瀬を連想させる映像スタイルを評価
- 批判的意見:「複雑な構造が冗長」「描ききれない社会背景」などの指摘も一部にあります。
総評:記憶と贖罪、母と娘を繋ぐ“赦しの物語”
『遠い山なみの光』は、カズオ・イシグロの文学の核である「不確かさ」「記憶」「喪失」への問いを、現代日本映画として丁寧に紡ぎ出した稀有な映像作品です。母を理解し、赦す娘の物語は、語られなかった過去もまた人生の一部として肯定する強さを与えてくれます。
※映画紹介についての一連の記事はこちらにまとめていますので、是非一読ください。