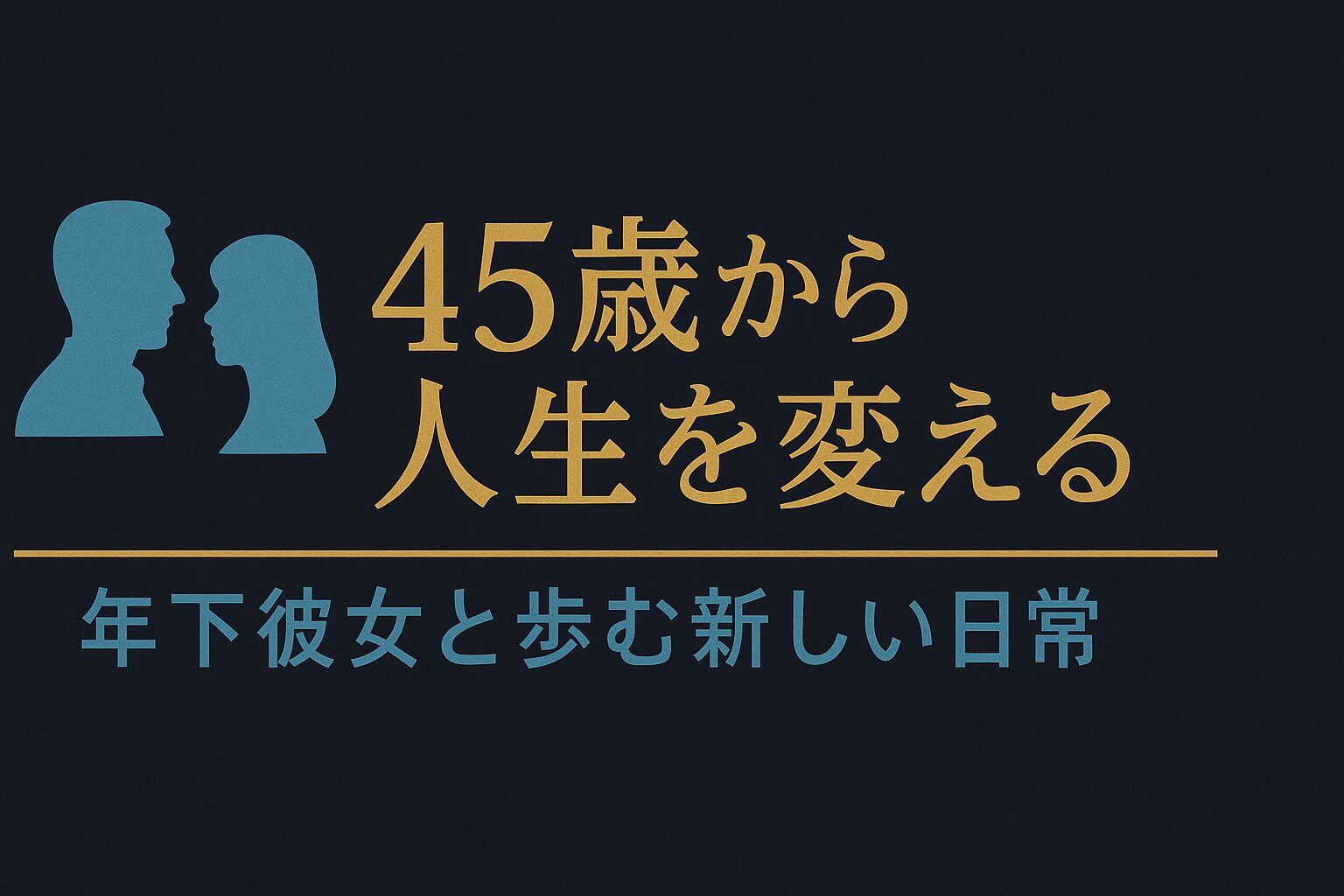はじめに
2025年9月12日公開の映画『ベートーヴェン捏造』は、かげはら史帆のノンフィクション書籍を原作に、脚本バカリズム、監督関和亮というチームが送る、音楽史と嘘の交錯するドラマです。秘書シンドラーの視点を通じ、偉大な作曲家ベートーヴェンの“神聖視されたイメージ”はいかにして創られたのかを描き、芸術と真実、崇拝と誤解を問いかける一作となっています。
🎬 映画情報・概要
- 監督:関和亮
- 脚本:バカリズム
- 原作:かげはら史帆『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』
- 主演:山田裕貴(シンドラー)、古田新太(ベートーヴェン)
- 共演:染谷将太(ジャーナリスト・セイヤー)、神尾楓珠、前田旺志郎、小澤征悦、生瀬勝久、小手伸也、遠藤憲一 他
あらすじ
youtube 松竹チャンネルより引用
舞台は19世紀のウィーン。難聴(耳が聞こえない)という重いハンディキャップを抱えながらも、多くの名曲を残した作曲家ベートーヴェン。その崇高なイメージは、秘書であるアントン・フェリックス・シンドラー(山田裕貴)が、彼の死後に仕立て上げた“聖なる天才音楽家”というイメージが作られたものだった――
シンドラーは、どん底の自分をベートーヴェンによって救われたと信じており、その恩義と憧れから、ベートーヴェンの“本来の姿”(暴力的・癇癪・不潔さ・偉大さと同時に人間らしい弱さ)を秘密裏に知りながら、世間には伝わらないようにしていた。
やがて、若きアメリカ人ジャーナリスト・セイヤー(染谷将太)が、ベートーヴェンの伝記をめぐる記事を書こうとする中で、シンドラーの“捏造”が明るみに出そうになり、真実と嘘の間で衝突が始まる。
\映画「ベートーヴェン捏造」の公式HPも是非参照ください/
映画『ベートーヴェン捏造』大ヒット上映中!
演出・映像・音楽:崇高と下世話の対比の美学
映像・美術
関和亮監督は、19世紀ウィーンの雰囲気を緻密に再現しつつ、ベートーヴェンの「公的な場」と「私生活」のアンバランスを映すことで、シンドラーの視点に観客を立たせます。
豪華な宮殿や演奏会場での光の具合、衣装の質感、照明の陰影が、ベートーヴェンを“神格化”する場面と、“人間としての粗さ”を見せる場面との差異を際立たせています。
音楽の演奏と録音品質にもこだわりが見られ、観客は耳でベートーヴェンを“体感”する瞬間を持てます。
脚本・構成
脚本のバカリズムは原作のノンフィクションを尊重しつつ、ドラマとしての魅力を加える調整を行っています。
シンドラーの心理描写、ジャーナリストとの対峙、伝記出版を巡る勢力間の争いなど、歴史と想像力が入り混じる構造を組み、観客が“何が真実か”を考え続ける形式を取っています。抜けのある展開ではなく、伏線の張り方や情報の開示タイミングが巧妙です。
音楽の使い方
映画はクラシック楽曲、特にベートーヴェンの有名な作品を劇中で多数使用し、それがシンドラーの語る“聖なるイメージ”を観客に刷り込む役割を果たしています。
同時に、“真実のベートーヴェン”を見せる場面では、その崇高な音楽が“ずれ”を伴うように演出され、愛憎や疲労、矛盾を聴覚でも感じさせる工夫がされています。
キャラクター・演技:崇拝、疑念、忠誠と裏切り
シンドラー(山田裕貴)
主人公。秘書としてベートーヴェンを深く愛し、その崇高な偉人像を守りたいという強い使命感を持ちます。その愛ゆえに、捏造という手段を選ぶことになり、その選択の重さ、嘘を生きる重荷、葛藤が演技の中心です。
山田裕貴は、忠実な熱意と、それと同時に誇張された嘘を隠す疲弊を表情で見せており、「愛が狂気になる瞬間」を説得力を持って演じています。正にシンドラーのベートーヴェンへの狂信的な執着を上手く表現しています。
ベートーヴェン(古田新太)
音楽界で英雄視される空気の中にある中で、人間らしい弱さ、癇癪、孤独、そして創作への情熱などがコミカルに表現されています。古田新太は、偉大な作曲家としての重みも、ひとりの人間としての汚れ臭さも併せ持つ役を演じ、崇拝対象と真実とのギャップを見せます。聴覚障害というハンディキャップも、ストーリー的な重要性だけでなく、彼の演技に幅を与えています。
ジャーナリスト・セイヤー(染谷将太)
セイヤーは“嘘を暴く者”であり、最初はシンドラーが著した伝記のベートーヴェン像に心酔していたが、ジャーナリストとして調査を進めるうち、伝記とはかけ離れた事実が浮かび上がる中で、そのギャップに落胆、怒りさえ感じていきます。
この心の動きは、正に観客の想いを代弁するかのように描かれており、最終的には自身のベートーヴェン偶像への憧れと、真実の間で葛藤することになります。
彼の心の葛藤が、他の秘書候補、伝記を書こうとする人々、学者、マスコミなど、それぞれ“どの真実を信じたいか”、真実がひとつでないということを表しています。
歴史、真実、観念の嘘
真実とはなにか? 捏造されたイメージとそれを受け入れる世間
この映画の核は、「私たちが信じている偉人像」がどのように形成されるか、そしてそれはどれほど“意図的”であるかを問いかけることです。シンドラーの嘘は、単なる誤解や美化ではなく、一種の“歴史プロデュース”です。
彼は崇拝者を満足させるため、あるいはベートーヴェン自身を“理想化された像”として世間に神格化させるために、記録や証言を操作し、伝記を方向づけていきます。
これはある意味、現代でのメディアによるプロデュースとも重なります。メディアによるコンテンツが、真に出演者の本質を描いているとは断言できません。そこには、「視聴者が見たい偶像」が映し出されているだけである可能性も大いにあるのです。
情報戦とメディアの役割
映画は“情報”がどう伝わり、どのように偽りが見過ごされるかを丁寧に描写しています。ベートーヴェンの伝記を出版する側の争い、秘書としての競争、メディアの反応などが絡み合い、真実とは何かを知ることが“力”であり、情報を握ることが人を作るということが示されます。
そして、劇中では伝記の内容の真贋を確認するために不可欠な根拠資料についても、捏造されたり、検証されたくない物については焼却されたりと、現代でも行われているであろう捏造改ざん、証拠隠滅を彷彿とさせるようなシーンも描かれています。
シンドラーの倫理的曖昧さ
シンドラーは完全な悪人ではない。むしろ、彼の行動は“愛”から始まったと言えるでしょう。しかし、その愛が誤解と歪みを生み、周囲にも影響を及ぼす。
彼がベートーヴェンの“聖なるイメージ”を作り上げる過程で無視した事実、隠した弱さ、被った被害もある。それでも、彼は、彼にとってのヒーローであるベートーヴェンの神格化にこだわり続けた。その一貫した姿勢は、倫理的には非難されるべきものであったとしても、プロデューサーとしての思想には一定の整合性はあったと言えるだろう。
考察:深掘りテーマと問いかけ
① なぜ私たちは偉人を神格化したがるのか?
偉人はしばしば「完璧さ」「理想」の象徴として描かれますが、人間らしい弱さや欠点が隠されていることも多いです。本作が示すのは、偉大さをたたえるあまり“嘘”を含む伝記が作られてしまうこと。そして、その神格化が持つ眩しさと危険性。観客は“聖人ベートーヴェン”を信じてきた側面があるかもしれませんが、この映画は「その光背の裏側」に目を向けさせます。
② 愛が捏造を生むとき
シンドラーがベートーヴェンを“下品で小汚いおじさん”として知りつつ、それを隠し、より崇高な姿に変えていくのは、愛ゆえの行動です。だが、この“愛”は自己満足、誇り、虚像を守りたい欲望、そして他者からの評価を気にする心が混ざっています。真実を守ることと、崇拝されることの間の戦いが、シンドラーという人物像に重層的な深みを与えています。
③ 嘘が暴かれた後の「救い」について
映画の後半で、ジャーナリストや後任の人々が動き、嘘が徐々に疑われていきます。この“暴かれる可能性”と“世間がそれを受け入れるかどうか”が、物語の緊張を作る核心です。嘘が明るみに出ても、完全な崩壊とは限らず、その後の選択が人を定義するというメッセージがあります。シンドラーにとって、嘘をついたことと、それを守ること、それを認められること、その全てが彼の人生の一部です。
④ 観客としての立場:我々はどの偉人像を信じてきたか?
この映画は観客に「自分自身が信じてきた偉人像や歴史の物語」がどれほど“編集されたもの”であるかを問いかけます。例えば学校で教えられた史実、伝記、小説、美術作品で描かれた偉人像――それらはどれほど真実と一致しているのか? どれだけが“語られなかった部分”を省略しているのか? この問いを抱かせる映画です。
感想:面白さとともに抱える失望と期待
全体として、『ベートーヴェン捏造』は非常にエンタテインメント性が高く、観客を引き込むドラマ性を持っています。歴史映画+ミステリー+人間ドラマという組み合わせがうまくまとまっており、感情の起伏、人物の対立、音楽の威力が効いています。
良かった点:
- シンドラーという複雑な主人公を、愛と嘘の間で揺れる人物として描いたこと
- ベートーヴェンの音楽が持つ力を、映像と音響で実感させる演出
- 真実を追い求めるジャーナリスト役との対立、そして信憑性を問う展開
惜しい点:
- 嘘と真実の境界線があまりにもはっきりしすぎて、観客が“どちら側にも共感できる曖昧さ”を求める場面ではやや強引に感じることがある
- 登場人物が多く、それぞれの背景が浅く終わってしまうキャラもいる
- 歴史ノンフィクションとしての信憑性をどこまで重視するかという点で、フィクションとしてのアレンジ部分に異論を唱える視聴者も出そう
総評:偉人像の裏側を覗く鏡として
『ベートーヴェン捏造』は、単なる歴史物語でも単なる伝記映画でもなく、“偉人神話の裏側”をエンタメとして提示する意欲作です。シンドラーという人物を通じて、愛、崇拝、嘘、真実、誤解、罪、そして赦しまでを描くことで、偉人とは何か、人はなぜ歴史に歪められた像を受け入れるのか、という根源的な問いを投げかけます。
音楽ファン、歴史好き、また“偉人伝”に疑問を持っている人には強くおすすめできる映画。スクリーンの大音量でベートーヴェンの名曲を聴きながら、この“でっちあげ”という嘘が持つ力と影響を考えさせられる時間となるでしょう。
※映画紹介についての一連の記事はこちらにまとめていますので、是非一読ください。